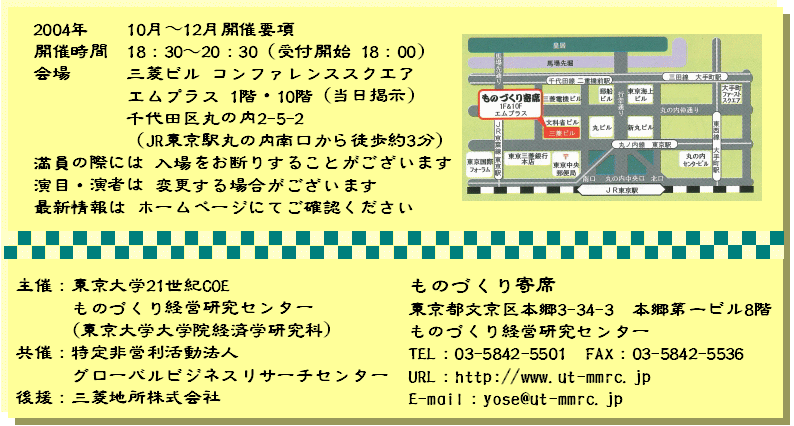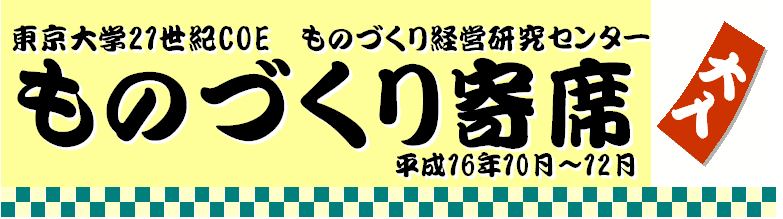
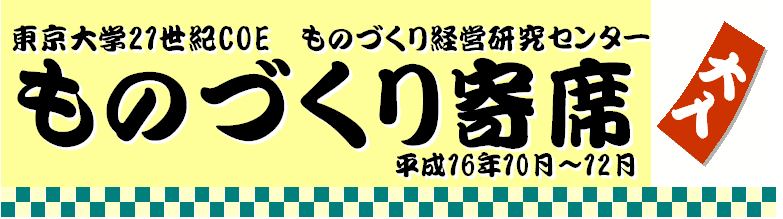
|
ものづくり寄席からのお知らせ 9月21日 大変お待たせいたしました。10月以降のスケジュールを更新しました。 ものづくり寄席からのお知らせ 7月28日 GBRCが発行しているオンライン・ジャーナル『赤門マネジメントレビュー』に、「ものづくり寄席」の要約が掲載されることとなりました。7月25日発行号には、1〜4回まで掲載されています。 各回A4一枚ですが、写真や図表などもあり、寄席の雰囲気を、感じ取っていただけると思います。 是非、ご覧下さい。 http://www.gbrc.jp/GBRC.files/journal/index.html#Akamon ものづくり寄席からのお知らせ 7月7日 「ものづくり寄席」を共催しているGBRCが毎週月曜日に発行しているメルマガ『GBRCニューズレター』では、「今週と来週のものづくり寄席」のコーナーがあり、「ものづくり寄席」の最新の情報が紹介されています。 『GBRCニューズレター』のバックナンバー&無料配信登録はこちらから↓ http://www.gbrc.jp/GBRC.files/newsletter/index.html ものづくり寄席のチラシ(PDF)はこちら ものづくり寄席チラシ(平成16年7月〜9月)PDFファイル以前のものづくり寄席のホームページはこちら ものづくり寄席チラシ(平成16年7月〜9月)htmlファイル |
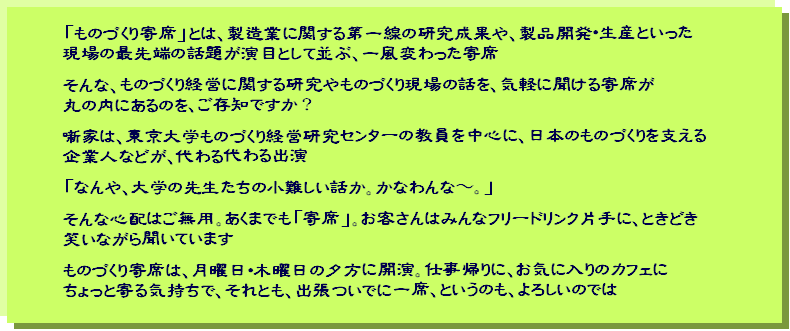
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
![]()
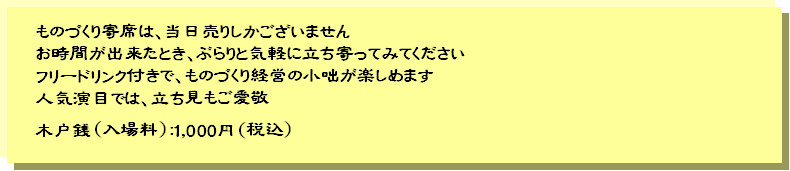
![]()

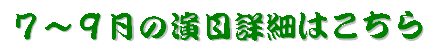
 |
|||
| 4日 (月) |
新宅 純二郎 東京大学大学院経済学研究科助教授 |
アーキテクチャの眼鏡で眺めた中国・アジア企業の実力 | 中国、韓国、台湾などの経済発展の中で急速に成長したローカル企業がもつ優位性と問題点をアーキテクチャの視点から覗いてみる。 |
| 7日 (木) |
小川 紘一 ものづくり経営研究センター特任研究員 元 富士通(株)光ディスク事業部長 |
製品アーキテクチャから見た技術拡散とアジアの産業興隆 | CDやDVD産業を製品アーキテクチャの視点から分析し、アーキテクチャが技術の拡散スピードに与える影響および日本・台湾・韓国企業の競争力に与える影響を解説する。 |
| 18日 (月) |
下川 浩一 東海学園大学大学院経営学研究科教授 法政大学名誉教授 |
世界自動車産業のグローバル再編成とその帰結 | 自動車産業のグローバル再編成の嵐がふきあれたのは、つい5年ほど前であった。しかしその後、再編統合の動きが行き詰まったのはなぜか、そして今後の行方はどうなるかをみてみたい。 |
| 21日 (木) |
高井 紘一朗 ものづくり経営研究センター特任研究員 元 アサヒビール(株)専務取締役 |
アサヒビールの品質保証は「太鼓判システム」から | 出荷するビールの品質をいかに保証するかという課題に対し、アサヒビールは家電の個人名の検査印をヒントにして、1本1本に保証印を捺すという視点の「太鼓判システム」を生み出した。 |
| 25日 (月) |
日野 三十四 広島大学大学院社会科学研究科教授 |
インテグラル型製品のモジュール化理論と方法論 | モジュール化は世界の産業・経済を大きく発展させた。今後の課題はインテグラル型製品のモジュール化であり、実践を通じての理論化・方法論化の試みを紹介する。 |
| 28日 (木) |
田中 正 ものづくり経営研究センター特任研究員 元 川崎三菱自動車販売(株)社長 |
ものづくりのカイゼン、販売営業活動への活用(2) | 前回は、トヨタ販売会社のカイゼン全般のお話。今回は、観察からの理論展開、競争力の深層と裏層、メーカーの係わり合いなど、さらに突っ込んでみたい。 |
 |
|||
| 1日 (月) |
高橋 伸夫 東京大学大学院経済学研究科教授 |
育てる経営とは何だろうか | 『虚妄の成果主義』以降、講演や取材で質問されることへの回答として、日本型年功制の考え方や思想を「育てる経営」として整理して提示してみたい。 |
| 4日 (木) |
大鹿 隆 ものづくり経営研究センター特任教授 |
生産性の諸問題と日本自動車産業の裏の競争力 | 日本製造業の中では自動車は業績面で絶好調であり、トヨタ、ホンダ、日産は最高益を更新し続けている。この背景を生産性の諸問題・裏の競争力を通してみると何が見えるかを語る。 |
| 8日 (月) |
呉 在恒 ものづくり経営研究センター特任助教授 |
ものづくりと情報技術(IT) | 情報技術自体は競争能力構築に必要条件ではあるが、十分条件ではない。この問題について、開発・調達・生産・販売の事例を紹介して考えてみたい。 |
| 11日 (木) |
伊藤 洋 ものづくり経営研究センター特任研究員 元 ホンダエンジニアリング(株) |
ものづくりからみたホンダの原点と進化 パート2 | パート2では過去、現在の車作りから、社会の変化にともない、将来の車と、車作りのあり方を考えてみる。あくまでも予想に過ぎないが。 |
| 15日 (月) |
小澤 茂幸 ものづくり経営研究センター特任研究員 よこはま大学ベンチャークラブ理事 |
企業はなぜ変革できないか? | 日本企業の多くが空前の高収益といわれています。本当に企業は変わったのでしょうか? |
| 18日 (木) |
松井 幹雄 ものづくり経営研究センター特任研究員 拓殖大学商学部教授 |
経営戦略よもやま話 | 「日本企業は戦略に弱い」といわれてきたが本当だろうか。特効薬のような「戦略アイデア」は存在するのだろうか。また最近「実行力」が大切だという意見もあるが・・・・。 |
| 25日 (木) |
藤本 隆宏 東京大学大学院経済学研究科教授 |
アーキテクチャとはなにものであるか | アーキテクチャとはそもそも何のことであるかを、いま一度説明します。上級者は入場お断りです。 |
| 29日 (月) |
斎藤 俊幸 イング総合計画株式会社代表取締役 関東学院大学社会環境システム学科非常勤講師 |
地域間競争〜生き残りのかたち | 日本の瓦産地は三河、淡路、石見のみが生き残った。3産地が地域間競争の中で形成したかたちから見えてくる地域再生の方向性を語る。 |
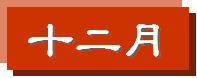 |
|||
| 2日 (木) |
天野 倫文 ものづくり経営研究センター特任研究員 法政大学経営学部助教授 |
中国家電企業の急成長と国際化に向けた課題−海爾と海信の事例 | 中国企業の発展は今後も続くか。中国の家電企業の急成長を支えてきた背景や要因を整理するとともに、その脆弱性や国際化に向けた課題についても議論し、日本企業のかかわり方を考える。 |
| 6日 (月) |
和久本 芳彦 ものづくり経営研究センター特任研究員 元 東芝(株)専務取締役 |
戦略的ビジネスとしてのライセンス | 技術開発・移転に係わるライセンスが経営全般に及ぼす影響は甚大である。 グローバル化の進展と共に、ライセンスを戦略的ビジネスとして展開する必要性と留意点を語る。 |
| 9日 (木) |
吉岡 伴明 フライシュマン ヒラード ジャパン(株) 元 ホンダアクセス(株)専務取締役 |
「物の観かたと考え方」と故本田宗一郎社長の考え方 | アイデアの原点は身近にある、よく物を観る事でおのずと色々な事が発想につながる、その観かた考え方を実例で解説。また、故本田宗一郎社長の物の考え方を体験から紹介。 |
| 13日 (月) |
片平 秀貴 ものづくり経営研究センター特任教授 丸の内ブランドフォーラム代表 |
ブランドづくりの三位一体:ディズニーの夢、トヨタの理、伊東屋の礼 | 強いブランドを生む組織には、顧客の先の夢を見る力、理詰めで技術を磨く力、顧客をきちんとおもてなしできる力が備わっています。ディズニー、トヨタ、伊東屋を例に、この「三位一体」の重要性を語ります。 |
| 16日 (木) |
安田 雪 ものづくり経営研究センター特任助教授 |
協豊会 − トヨタを支えるサプライヤのネットワーク | トヨタのサプライヤ企業が形成する協豊会。協豊会参加企業の相互取引関係を、ネットワーク分析を用いて抽出し、構造の頑健性と脆弱性を考える。 |